
| この記事でわかること |
|
| この記事の対象者 |
|
| 期待できる効果 |
|
企業のDX推進部、そして特に会計・法務といった高度な専門知識を要するソフトウェアを提供するカスタマーサポート(CS)部門の皆様へ。
CS業務の裏側で、オペレーターが最も時間を費やし、最もストレスを感じる作業は何でしょうか。それは、「顧客の複雑な質問に対し、膨大な社内マニュアルや技術ドキュメントの中から、正解となる情報を探し出す」という「検索」作業ではないでしょうか。
「マニュアル検索に時間がかかり、顧客を待たせてしまう…」 「新人オペレーターは、ベテランと同じ品質の回答ができない…」 「知識の属人化が、応対品質の均質化を阻んでいる…」
この課題は、ソフトウェア開発・販売を行う株式会社ミロク情報サービス(MJS)のような、高度な専門性(Expertise)が求められるBtoB企業のCS現場では特に深刻です。この「検索時間」と「知識の壁」という構造的な課題に対し、MJSは生成AIを活用した問い合わせ対応システムを開発し、2024年10月より自社のCS部門で利用を開始しました。
本稿では、MJSのAI導入事例を基に、生成AI(RAGシステム)がCS部門にもたらす3つの決定的な変革を解説します。AIを「知識の番人」とすることで、いかにしてCSの効率、品質、そして育成という3つの要素を同時に最適化できるのか、その具体的な戦略を見ていきましょう。
専門サポートの構造的課題:知識の海での「溺れ」を防ぐAI
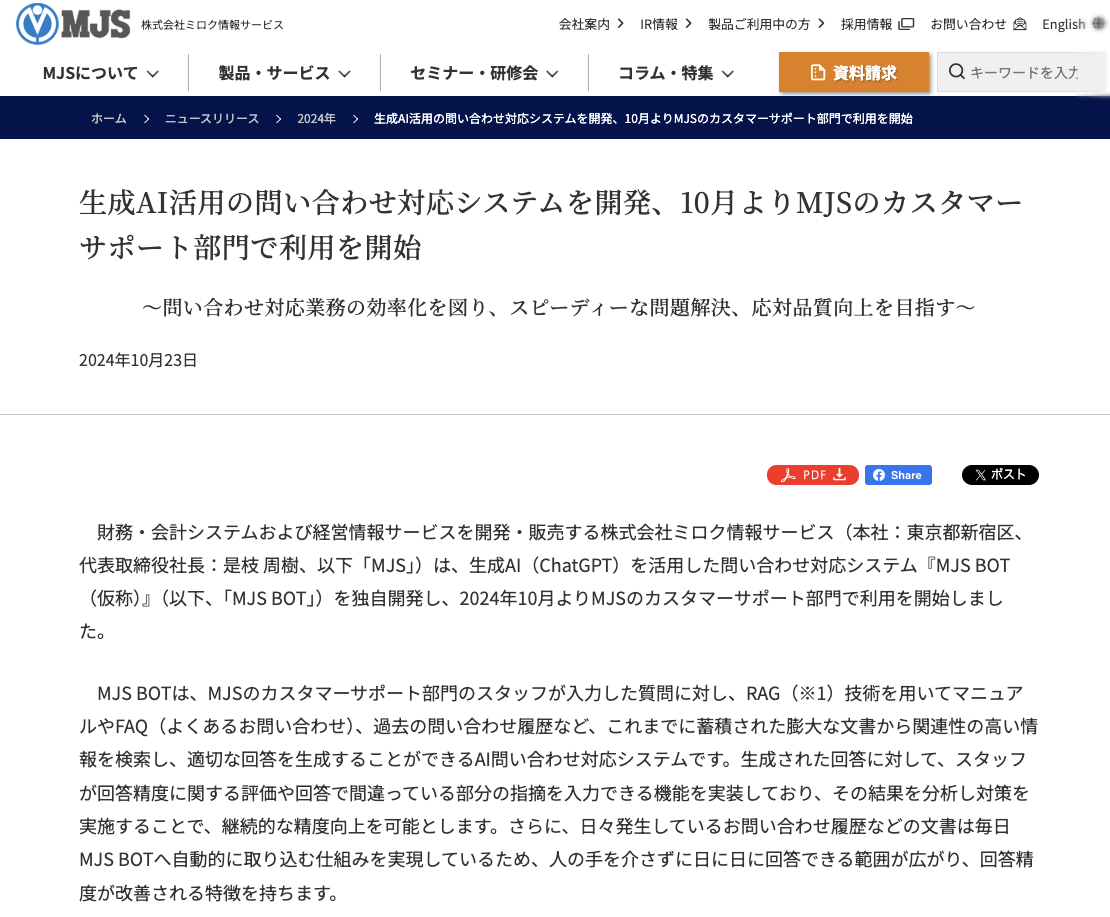
オペレーターを疲弊させる「手動での知識検索」の非効率
MJSのCS現場が直面していた最大の課題は、「情報の探索コスト」でした。顧客の質問に対する正解は、マニュアル、技術文書、過去の対応ログといった、複数のドキュメントに散在しています。
- 課題1:探索時間の浪費: オペレーターは、これらの膨大な知識の中から、正しい情報を手動で検索し、読み解き、回答文に整形するという、非生産的な作業に多くの時間を費やしていました。これが、顧客を待たせる原因となり、顧客満足度を低下させていました。
- 課題2:知識の属人化: ベテランオペレーターは、「どのマニュアルの、どのページに正解が書かれているか」という暗黙知を持っているため、迅速に対応できますが、新人はその知識がないため、応対品質に大きなバラつきが生じていました。
AIによる解決:RAGを活用した「ナレッジの民主化」
MJSが開発したシステムは、生成AIのRAG(検索拡張生成)技術を活用し、この「知識の壁」を打ち破ります。
- 知識ベースの構築: MJSの社内マニュアル、技術ドキュメント、Q&A集といったすべての知識をAIの知識ベース(ベクトルデータベース)に登録します。
- AIによる文脈理解: オペレーターが顧客からの質問(例:〇〇というエラーが出たが、どうすればいいか)をシステムに入力すると、AIがその質問の文脈を理解し、知識ベースの中から最も関連性の高い情報を瞬時に抽出します。
- ドラフト生成: 抽出された情報に基づき、LLMがそのまま顧客に送信できるような回答のドラフトを自動で生成します。
AIが「検索→抽出→ドラフト生成」というプロセスを自動で担うことで、オペレーターは「情報探索」という低付加価値の作業から解放されます。
MJSが実現した3つの決定的な変革
MJSが目指すのは、単なる業務効率化に留まらない、CS部門の品質、スピード、そして人材育成という構造的な変革です。
変革1:オペレーターの効率化と顧客対応のスピード向上
最も直接的な効果は、検索時間の劇的な短縮です。
- 検索工数の削減: オペレーターが手動でマニュアルを検索し、回答を作成する時間が大幅に短縮されます。これにより、顧客の待ち時間が短縮され、顧客満足度の向上に直結します。
- 応答品質の均質化: ベテランの知識に依存していた回答が、AIが参照した客観的な知識ベースに基づくものとなるため、回答の品質と一貫性が確保されます。
変革2:新人育成期間の短縮と専門性(Expertise)の早期獲得
AIが「リアルタイムのメンター」として機能することで、新人オペレーターの育成期間が短縮されます。
- リアルタイムサポート: 新人オペレーターでも、ベテランと同様に、AIが生成した正確な回答ドラフトを参照して応対できるため、経験不足による回答の遅延やミスを防げます。
- 知識の習得: AIが生成した回答の「根拠となるマニュアルの該当箇所」も同時に表示されるため、新人は実務を通じて効率的に知識を身につけることができ、専門性(Expertise)の早期獲得に繋がります。
変革3:人間による「共感」と「AIの育成」への集中(Experienceの向上)
AIが定型的な情報提供を担うことで、オペレーターは人間にしかできない業務に集中できます。
- 共感の提供: オペレーターは、AIが生成した論理的な回答に、「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」といった共感の言葉や温かいニュアンスを加えて、顧客との信頼関係を構築します。
- AIの育成(Experience): オペレーターは、AIの回答が不十分だったり、より良い回答方法を発見したりした場合、その最良の回答をAIの知識ベースにフィードバックします。この「AIを育てる」プロセスが、オペレーターの新しい経験(Experience)となり、組織全体のナレッジを継続的に高めます。
AI CS導入におけるDX推進とセキュリティの論点
MJSの事例が示すように、生成AIをCSに導入する際は、技術だけでなく、セキュリティと運用体制の整備が不可欠です。
倫理とセキュリティ:機密情報の保護(情シス向け)
CS部門は、顧客情報や機密性の高いエラー情報を扱うため、AI活用においてセキュリティが最重要課題となります。
- プライベートRAG環境: MJSのように、自社のナレッジベースをAIの知識源とするプライベートRAG環境を構築することで、入力データが外部のLLMの学習に使われるリスクを回避します。
- 情報漏洩対策: 顧客の機密情報(個人情報、支払い情報など)がAIの回答生成プロセスで誤って外部に流出しないよう、データのマスキングやアクセス制御を徹底します。
AIの継続的な「育成」体制の構築(DX・人事部向け)
AIを導入して終わりではなく、「現場の経験」をAIにフィードバックし続ける体制が、成功の鍵となります。
- フィードバックの仕組み: 「AIの回答を修正した場合、ワンクリックで最良の回答をナレッジベースに登録できる」といった、オペレーターの負担にならないフィードバックの仕組みを構築します。
- 評価とモチベーション: AIの育成に貢献したオペレーターを適切に評価し、「AIの先生役」という新しい役割に対するモチベーションを高める人事制度を設計することが、DX推進部と人事部の重要な役割となります。
結論:AI CSは「人間中心の顧客体験」を実現する
MJSの生成AI活用事例は、AIが人間を代替するのではなく、人間の能力を拡張し、最もストレスの多い作業から解放してくれるという、人間中心のDXの理想形を示しています。
AIが知識の網羅とスピードを担保することで、オペレーターは「お客様の不安に寄り添う」という、人間にしかできない、最も価値のある業務に集中できます。
AIをCS部門の「最強の相棒」として迎え入れ、応対品質の均質化、新人育成の効率化、そして顧客との信頼(Trust)という資産の積み上げを実現させましょう。この戦略こそが、AI時代における企業の競争優位性を確立する鍵となります。
