
| この記事でわかること |
|
| この記事の対象者 |
|
| 効率化できる業務 |
|
「ウチの会社の若手、本当に仕事してるか?」
もしあなたが企業の経営企画部や人事部、あるいはDX推進の担当者で、こんな疑問を漠然と抱いているとしたら…。その認識、もしかすると根本的に間違っているかもしれません。
彼ら(彼女ら)は、私たちが想像もしていないツールを使いこなし、とんでもないスピードで業務を処理している可能性があります。
衝撃的なデータが飛び込んできました。 日本リサーチセンター(NRC)が2025年9月に実施した調査によると、20代の生成AI利用率が、ついに5割を超えたというのです(男性55%、女性51%)。
20代の、実に2人に1人。
これはもう「一部のITマニアが使っているツール」ではありません。彼らにとって生成AIは、私たちがExcelの関数を使うのと同じか、それ以上に「当たり前」の業務インフラになりつつあるのです。
この記事を読んでいるあなたは、きっとこう思っているはずです。
- 「若手はそんなに使っているのに、なぜ自社の生産性は上がらないんだ?」
- 「ChatGPTが騒がれて久しいが、結局『次』はどれなんだ? Copilot? Gemini?」
- 「情シスとして、セキュリティは本当に大丈夫なのか?」
この記事は、単なる最新ニュースの解説ではありません。 この「AIネイティブ世代」の台頭という“不可逆な波”を、あなたの会社がどう乗りこなし、競争力に変えていくか。そのための具体的なヒントと、今すぐ確認すべきアクションを提示します。
衝撃の事実。20代の2人に1人が生成AIを使いこなす時代
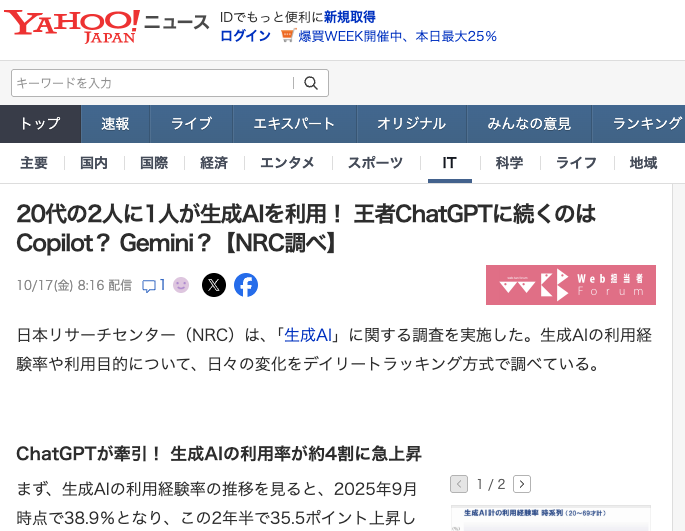
NRC調査が示す「AIネイティブ」の台頭
今回のNRCの調査結果は、私たちビジネスパーソンに強烈な事実を突きつけました。
- 20代男性:55%
- 20代女性:51%
この数字は、他の世代と比べても突出しています。 同調査によれば、生成AIの利用率は2023年3月時点では全世代で5%未満でした。それが2024年9月には2割を超え、2025年に入ってからも急上昇を続けています。
まさに「爆発的普及」。
この背景にあるのは、もはや「ChatGPTがすごい」という単純な話ではありません。 20代のデジタルネイティブ層が、生成AIを「検索エンジンの次」あるいは「優秀なアシスタント」として、ごく自然に生活や業務に取り込み始めた、という構造的な変化です。
彼らは「AIに仕事を奪われる」といった旧来型の議論にはあまり興味がなく、「いかにAIを使い倒してラクをするか、成果を出すか」という点に極めて現実的(シビア、とも言えます)なのです。
なぜ若者はAIを使いこなすのか? 主な用途トップ3
では、彼らは一体「何に」使っているのでしょうか?
「どうせチャットで遊んでいるだけだろう」 そう思うのは早計です。NRCの別調査(2025年6月)によれば、利用用途の上位は非常に実務的です。
- アイデア出し (32.8%)
- メールや文書の作成 (24.0%)
- 翻訳・通訳 (22.6%)
これを見て、ピンと来ませんか? これらはすべて、かつて私たちが「うーん…」と頭を悩ませ、多くの時間を費やしてきた作業そのものです。
- 企画部の若手が、AIとブレストしながら企画書のタタキ台を1時間で作り上げる。
- 人事部の新人が、難解な社内規程のドラフトをAIに要約させ、分かりやすいQ&A集を即座に作成する。
- 営業担当が、海外の最新市場レポートをAIに翻訳させ、次の日の朝礼で「インサイト」として発表する。
これが、今まさに起きている現実です。 彼らはAIを使って「ゼロから1を生み出す苦痛」や「面倒なルーティンワーク」を回避し、より創造的な「1を10にする作業」に時間を使おうとしています。
「ポストChatGPT」三つ巴の戦い。CopilotとGemini、企業導入のリアル
20代がAIを使いこなしている事実は分かりました。 では、企業のDX推進部や情シス部の視点に立った時、「どのAIを公式導入すべきか?」という悩ましい問題が浮上します。
いまだに「生成AI=ChatGPT」というイメージは強いですが、水面下ではMicrosoftの「Copilot」とGoogleの「Gemini」が、企業向け市場で熾烈な覇権争いを繰り広げています。
この2つ、似ているようで「得意分野」が全く異なります。 あなたの会社のIT環境や業務フローによって、選ぶべき最適解は変わってくるのです。
王者ChatGPT:依然強い「壁打ち」相手
まず、王者ChatGPT(OpenAI)です。 その強みは、何と言っても「対話の自然さ」と「発想力」。
とりあえず困ったらChatGPTに投げてみる、という「壁打ち」相手としての信頼感は抜群です。特定の業務システムに縛られないため、あらゆる部署の「アイデア出し」や「一般的な文章作成」において、今なお最強のパートナーと言えるでしょう。
- 向いている部署:企画部、マーケティング部、広報部
- 企業導入の懸念:標準プランでは入力したデータが学習に使われるリスク。セキュリティを担保するには「ChatGPT Enterprise」の契約が必須となり、コストがかさむ点がネックです。
Copilotの強み:情シスが喜ぶ「セキュリティ」と「Office連携」
次に、Microsoftの「Copilot」です。 (以前はBing Chatと呼ばれていましたが、今やMicrosoft 365にガッチリ組み込まれています)
Copilotの最大の強みは、多くの日本企業が依存している「Microsoft 365(Office)とのシームレスな連携」に尽きます。
- Teamsの会議中に、リアルタイムで議事録が生成され、タスクが自動でリストアップされる。
- Outlookで、膨大な未読メールを要約し、返信文案を3パターン提案してくれる。
- PowerPointを開き、「今期の営業実績データを使って、役員報告用のスライドを10枚作って」と指示するだけで、グラフ付きのドラフトが完成する。
これはもう「魔法」ではなく「現実」です。 さらに情シス部にとって魅力的なのは、「Copilot for Microsoft 365」を契約すれば、入力したデータが外部のAI学習に使われないとMicrosoftが明言している点です。
社内データ(SharePointやOneDrive内)をAIが学習し、社内の情報だけに基づいた回答を生成する「セキュアな社内版ChatGPT」を構築できる。これは、機密情報漏洩を何よりも恐れる企業にとって、非常に強力な導入理由となります。
- 向いている部署:情シス部、DX推進部、営業部、管理部門全般
- チェックポイント:既存のMicrosoft 365ライセンス(E3/E5など)が前提となるため、導入コスト全体の試算が必要です。
Geminiの強み:企画部が唸る「Google連携」と「分析力」
最後に、Googleの「Gemini」です。 (旧Bardですが、Googleの最強AIモデルの名を冠して生まれ変わりました)
Geminiの恐ろしさは、Microsoftとは逆のアプローチ。「Google Workspace(Gmail, Drive, Docs)との連携」と、Googleが持つ膨大なWeb情報、そして「高度な分析能力」です。
- Gmailの受信トレイで、過去の顧客とのやり取りをすべてAIが分析し、「この顧客が今求めている提案」を起案してくれる。
- Googleスプレッドシート上で、複雑な関数を組むことなく、「第3四半期の製品Aに関する売上トレンドを分析し、要因を考察して」と指示できる。
- Google検索の最新情報をリアルタイムで反映するため、市場調査や競合分析の「鮮度」が非常に高い。
特に30代の利用率が比較的高いというデータもあり、データドリブンな意思決定を求められるミドル層や企画・マーケティング担当者にとって、Geminiは「最強のリサーチ・分析アシスタント」となり得ます。
- 向いている部署:経営企画部、マーケティング部、人事部(採用トレンド分析など)
- チェックポイント:組織全体がGoogle Workspaceをメインで使っているかが導入効果を左右します。Microsoft環境がメインの会社では、その真価を発揮しづらいかもしれません。
【企業のホンネ】AI導入で見えた「理想と現実」
さて、ここまで各AIの理想的な活用法を見てきました。 ですが、実際に導入を進めるDX推進部や情シス部の現場からは、こんな「ホンネ」が聞こえてきそうです。
これは、私たちが日々の業務で耳にする、リアルな体験談です。
DX推進部の嘆き:「そのAI、シャドーITになっていませんか?」
「ウチもようやく全社でCopilotを導入したんです。情シスと連携してセキュリティも万全、『これで生産性爆上がりだ!』と期待していました。
ところが…先日、企画部のエースであるA君(28歳)のPCを覗いたら、彼はCopilotを使わず、ブラウザで個人の無料版ChatGPTを使っていたんです。
理由を聞いたら、『会社のCopilotは、なんか回答が“お行儀よすぎて”ダメなんですよ。発想が飛ばない。あと、社内データしか読まない設定になってるから、外部の最新トレンドが引けない』と…。
良かれと思って整備した公式ツールが使われず、結局セキュリティリスクのある野良AIが「シャドーIT」として使われている。DX担当として、頭が痛い問題です」(DX推進部・30代男性)
この悩み、非常に深刻です。 企業が「安全」のためにかけた機能制限が、かえって現場の「利便性」を奪い、結果として利用が定着しない。それどころか、管理外のAI利用(シャドーIT)を助長してしまう。
20代の利用率が5割を超えている今、彼らを「禁止」や「制限」で縛り付けるのは不可能です。 いかに「安全」と「利便性」を両立させるか。情シスと現場の密な対話が求められています。
人事部の期待:「AIスキルを採用・育成にどう活かすか」
「人事部としては、20代のAI利用率の高さは『脅威』ではなく『大きなチャンス』だと捉えています。
これまでの採用面接では、『ExcelでVLOOKUPが使えます』『PowerPointで資料が作れます』といったスキルが評価されていました。
でも、これからは違います。 『あなたは、どの生成AIを使って、どんなアウトプットを(どれくらいの時間で)出せますか?』 これが、個人の生産性を測る新しいモノサシになるはずです。
すでに、中途採用の現場では『前職でCopilotを使った業務改善経験』をアピールする若手が増えています。
私たちの課題は、こうした『AIネイティブ世代』のスキルをどう正当に評価し、入社後にどう活かしてもらうか。そして、既存の40代・50代の社員にどうやってAIスキルを“リスキリング”してもらうか。人事制度そのものを見直す時期に来ていると感じています」(人事部・40代女性)
AIスキルは、もはや「ITスキル」ではなく、「ビジネス基礎スキル」の一部です。 人事部や経営企画部は、この新しいスキルセットを組み込んだ評価制度や育成プログラムの策定を急ぐ必要があります。
今さら聞けない「生成AI導入」の疑問
ここまで読んで、「理屈は分かるが、具体的にどうすれば…」と悩んでいる方も多いでしょう。よくある3つの疑問にお答えします。
Q1. 結局、企業導入はどれが一番安全?
A1. 現時点での「安全神話」は存在しませんが、企業統制(ガバナンス)の観点では「Copilot for Microsoft 365」が一歩リードしています。
理由は、多くの企業が既に使用しているMicrosoft 365のセキュリティ基盤(Entra IDなど)の上で動作し、データが外部に流出しない設計になっているためです。 ただし、Googleも「Gemini for Google Workspace」で同様のセキュリティレベルを提供しており、甲乙つけがたい状況です。
最も危険なのは、「よく分からないから」という理由で、社員が個人契約の無料AI(ChatGPTやGeminiの無料版など)を業務で使うのを黙認することです。これが情報漏洩の最大の温床となります。
Q2. 社員のAI利用を「禁止」するのは悪手?
A2. ほぼ間違いなく「悪手」です。
20代の2人に1人が使っているツールを「禁止」しても、彼らは隠れて使います(=シャドーIT化)。 禁止するのではなく、「明確なガイドラインを引く」ことが正解です。
- 機密情報、個人情報、顧客情報は絶対に入力しない。
- AIの回答は鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行う。
- 著作権を侵害するような使い方はしない。
まずはこの3点を周知徹底させ、最低限のリスクヘッジを行うことが、情シス部やDX推進部の最初の仕事です。
Q3. 導入効果がイマイチ見えません…
A3. 「全社一斉導入」にこだわっていませんか?
生成AIは、部署や業務によって効果の出方が全く異なります。 まずは「AIで生産性が劇的に上がりそうな部署」を見極め、スモールスタートで試すのが鉄則です。
- 人事部:膨大な応募書類のスクリーニング、社内規程の要約
- 情シス部:ヘルプデスクの一次回答、簡単なスクリプト作成
- 企画部:市場調査レポートの要約、ブレスト
これらの部署で「月間〇〇時間の工数削減」といった具体的な成功事例を作り、それを全社に横展開していく。この地道なプロセスこそが、DX成功の鍵となります。
まとめ:「様子見」はもう終わり。企業が今すぐ取るべきアクション
20代の生成AI利用率が5割を超えた――。
この事実は、私たちが「AIを導入するか否か」を議論するフェーズが、とっくの昔に終わっていることを示しています。 もはや「AIネイティブ世代が使いこなすツールに、企業側がどう追いつくか」という問題なのです。
「まだ時期尚早」「ウチの業界には関係ない」と様子見を決め込んでいる企業は、この数年で、AIを使いこなす競合他社や、AIネイティブ世代が入社してくるスタートアップに、圧倒的な生産性(とアイデアの質)で引き離されていくでしょう。
この記事を読んだあなたが、経営企画、DX、情シス、人事のいずれかの担当者であれば、取るべきアクションは明確です。
- 「知る」:まず、自社の若手社員が「何を」「どれくらい」使っているか、匿名アンケートでも良いので実態を把握してください。シャドーITの現状を知ることが第一歩です。
- 「決める」:ChatGPT, Copilot, Gemini…どれでも構いません。「これなら安全」と会社が言える公式ツールを一つ決め、試験導入してください。
- 「引く」:禁止ではなく、「ガイドライン」という線を引いてください。リスクをゼロにはできませんが、最小化する努力はできます。
AIの波は、私たちが思っているよりずっと速く、深く、静かに押し寄せています。 その波に乗り遅れないために。まずはあなたの隣の席の若手社員に、こう聞いてみることから始めてみませんか?
「最近、仕事でどんなAI使ってる?」
