
こんにちは!AROUSAL Tech.広報部です。
本日は、AI使用を見抜くAIチェッカーの仕組みと対策についてお話しします。
「この文章、AIで書いたって思われないかな……?」
ChatGPTなどの生成AIを使ってレポートや記事を書いた経験がある方なら、一度はそんな不安を感じたことがあるのではないでしょうか。
最近では、教育機関や企業で「生成AIチェッカー」が使われるケースが増え、提出物がAIによるものかどうかをチェックされる機会も少なくありません。
しかし、チェッカーの仕組みや引っかかるパターン、そしてどのように手を加えるとよいかを知っていれば、必要以上にビクビクすることなく、自然な文章へと仕上げることは可能です。
本記事では、生成AIチェッカーに“バレる”仕組みや判定されやすい文の特徴を解説しつつ、AIっぽさを消すリライトのコツや実例を紹介します。安心して提出・公開できる文章を目指しましょう。
「これAIで書いた?」と疑われたらどうなる?まず知っておきたいリスクと背景

生成AIの普及により、文章のクオリティは手軽に上げられるようになりました。
一方で、「これ、本当に自分で書いたの?」と疑われるケースも増えており、学校や企業では生成AIチェッカーの導入が進んでいるのが現状です。
ここでは、AI使用を疑われたときに起こり得る状況や、チェックの背景にある社会的な流れを整理しておきましょう。
教育現場・企業で広がるAIチェックの実態
2023年以降、大学・高校などの教育機関では、ChatGPT等の使用を禁止・制限する方針を打ち出すところが相次ぎました。
特に論述式課題や卒論、小論文では「自分の思考や言葉で書くこと」が求められるため、AIによる自動生成は不正とみなされるリスクがあります。
同様に、企業でも「提出されたレポートや記事がAI丸写しではないか」を内部で確認する動きが強まっています。外部ライターとのやりとりでは、品質管理や著作権の観点からAI判定ツールを導入するケースもあります。
「生成AIの使用は禁止」と言われたら何が起きる?
提出前に「AIの使用は禁止です」と明言されている場合、AI使用=規約違反や不正行為として扱われる可能性があります。
学生ならレポートの減点・再提出・成績への影響、企業なら信頼失墜・契約解除といったリスクもゼロではありません。
特に問題になるのは、「人のふりをしてAIが書いた文章を出すこと」=意図的な偽装と判断された場合です。
このようなケースでは、本人の誠実性や評価にも傷がつく恐れがあります。
バレたときのペナルティや信用失墜のリスク
現時点で、生成AI使用に対するルールは機関によってバラつきがありますが、「バレる→一発アウト」というケースも現実に起きています。
- 学校:成績評価から除外/不正行為として処分対象
- ライター案件:再発注中止・報酬減額・クライアントの信頼喪失
- 社内提出物:能力や誠実さへの疑念
つまり、「AIを使ったことそのもの」よりも、「何も説明せず、“自分で書いたように見せかけた”ことの方が問題視されやすい」という傾向があります。
とはいえ、AIを“参考ツール”として活用している人は非常に多く、重要なのは「使い方」や「あくまで自分が書いたことがわかる工夫」の方です。
次章では、生成AIチェッカーが何を見て“バレた”と判断しているのか、その仕組みに迫っていきます。
生成AIチェッカーの仕組みとは?どんな文章が疑われやすいのか

「AIで書いた文章はバレる」と言われるのはなぜか?
そのカギを握るのが、生成AIチェッカーがどのような仕組みで判定を行っているかです。
ここでは、代表的なチェッカーが見ているポイントと、AIっぽさが出てしまう文章の特徴を解説します。
チェッカーは何を見て判定しているのか(語彙・文構造・自然さ)
AI文章判定ツールの多くは、確率論・文体パターン・言語的特徴に基づいてAI生成かどうかを推定しています。
主に以下のような点がチェック対象になります。
- 単語や文構造の繰り返しパターン:AIは安定した構文で出力しがち。似たような文が続くと「機械的」と判定されやすい。
- 語彙の多様性:人間が書いた文章は語彙が散らばるのに対し、AI文は確率的に選ばれた“無難な表現”が多くなる傾向あり。
- 文のばらつき:AI文は文の長さや構造が均質的。人間文は「短文+長文+感情表現」などバラつきがある。
つまり、「自然すぎる整った文章」こそ、逆に怪しまれるという皮肉な構造になっているのです。
「AIらしさ」の典型例と引っかかる文章パターン

以下のような文体は、多くのチェッカーで高確率で“AI生成の疑いあり”と判定される可能性があります。
- 「結論→理由→具体例→まとめ」など構成が機械的すぎる
例:「まず第一に〜、次に〜、最後に〜」
- 抽象的・無難な表現が続く
例:「テクノロジーの発展は、我々の生活に多大な影響を与えてきました。」
- 感情や主観がまったく入っていない説明口調
例:「〇〇は△△であるため、□□といえる。」
- 事実っぽく見えるが出典のない一般論
例:「多くの人がこのように考えています。」
こうした文章は、AIが最も得意とする「一般的・曖昧で破綻のない内容」に近いため、”AIが書いた”と判断されやすいのです。
判定スコアが高くなる“危険な使い方”とは?
- AIチェッカーは、以下のような使い方で一気に検出リスクが高まります。
そのままコピペで提出:生成直後の文章を一切手直しせず使用 - 複数段落を一気に出力した長文をそのまま貼り付け
- プロンプト内容が汎用的すぎて“AIらしい文体”に偏っている
- あまりにも論理が破綻していない(逆に不自然なほど整っている)
つまり、“整いすぎている文章”がかえって疑われるというケースがあるため、「AIっぽさ」を崩すためには、自分で手を加える工夫が必要になります。
次章では、こうしたリスクを回避するための具体的なリライト対策・自然文の作り方を5つのポイントに分けて解説していきます。
AIで書いたと思われない5つのリライト対策と自然文への落とし込み方
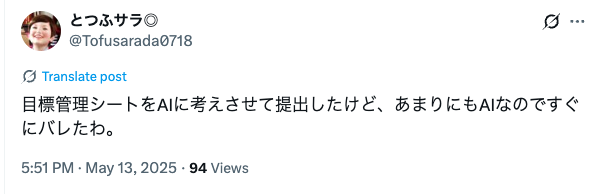
生成AIを使って文章を作成したあとに「このまま提出したら全部AIで書いたってバレるかも…」と感じたなら、人間らしさを加える“ひと手間”を入れることが大切です。
ここでは、生成AIチェッカーの判定をかいくぐるための具体的な5つのリライトテクニックをご紹介します。
1.一文の長さをばらつかせる/構文を崩す
AIの文章は整っていて文法的に完璧な反面、文のリズムが単調になりやすい傾向があります。
そこで、人間らしく見せるには以下のような工夫が有効です。
- あえて短文と長文を混ぜる
- 主語や文末のリズムを揺らす(〜だ。〜ます。〜かもしれない)
例:
AI文 →「この技術は私たちの生活を大きく変える可能性があります。」
リライト →「この技術、生活を変えるかもしれません。それも、私たちが想像している以上に。」
このように、体言止めや倒置法などを駆使することで、人間の文章らしい“ゆらぎ”を作ることができます。
2. 抽象語・テンプレ表現を避け、具体例を加える
AIは「包括的に、効率的に、利便性が高まる」など、抽象的な言い回しを多用します。
そのまま使うと“AIっぽさ”が残るため、以下のようにリライトしましょう。
- 抽象語は削る or 言い換える
- 具体的な体験談や数値、エピソードを入れる
例:
AI文 →「テクノロジーは私たちの生活を豊かにします。」
リライト →「たとえば、通勤中にスマホで家電を操作できるようになった。これが“生活が豊かになる”ということだ。」
3. あえて“人間らしいミス”や感情を混ぜる
AIは正確すぎるので、“少しヘタ”な文章がむしろ自然に見えることがあります。
- 「えっと」や「〜かも」など、迷い・感情・口語を少し入れる
- 断定を避けて推測・感想に変える
例:
AI文 →「この施策は、効果的であるといえる。」
リライト →「もしかするとこのやり方の方が効果あるんじゃないか、と私は考えています。」
4. 自分の経験や意見を必ず一部に入れる
人間らしさの最大の武器は、「個人の視点や体験」。
AIは“自分の実体験”を語れないため、そこに一文加えるだけで判定をかいくぐりやすくなります。
- 「私はこう感じた」
- 「実際に使ってみて〜だった」
- 「高校時代に〜という経験がある」
といった、人間ならではの思いや経験などを織り交ぜてみると、格段にチェッカーでの検出率が低くなります。
例:
AI文 →「運動は心身の健康に良い影響を与えます。」
リライト →「僕自身、大学時代に毎朝ジョギングを始めてからメンタルの調子が安定した。」
5. チェッカーにかけて反応を見る→再調整する
仕上げのステップとして、生成AIチェッカーに一度かけてみることも重要です。
- ユーザーローカルなどを使って生成率をチェック
- 高スコアが出た箇所を再確認し、手直しして再チェック
完全にバレない保証はありませんが、生成率が30%以下になるよう意識すると安全圏に近づきます。
「人間らしい文章とは何か?」を学ぶ機会にもなります。
信頼されるためにやっておくべき“人間味ある文章づくり”の習慣
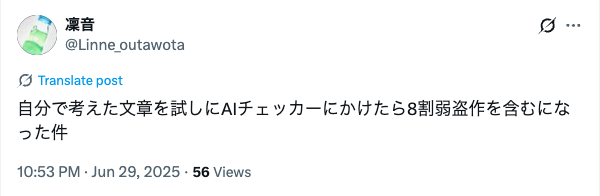
AIの力を借りること自体は悪ではありません。
しかし、そのまま提出することで「他人の力を借りてごまかした」と思われてしまえば、せっかくの成果も台無しです。
バレないためにリライトするという視点が、時に必要になる気持ちも理解できますが、それ以上に“読まれても納得される文章”を目指すことが、長い目で見て最も確実な方法です。
構成だけAI、肉付けは自分で行うハイブリッド活用
レポートや記事作成など、「すべてを一発でAIに出させたい」という気持ちはとても良くわかります。
しかし、AIでライティングするにあたって最も効果的にその実力を発揮できるのは、「構成づくり」です。
なぜなら、AIは、物事を体系だてて考えることに優れており、論理構成を作り出すことが上手なためです。
そのため、一度作成しようとしているレポートや記事については、必要な情報とゴールを与えた上で
「これらを体系立てて整理し、記事にするための構成を考えて」と命令してみましょう。
そこからの肉付けは案外むずかしくなく、それだけでもかなりの時間と労力の節約になりますよ。
AI出力に“言い換え癖”をつけると自然になる
AIの文章を読み慣れてくると、逆に「あ、これ人が書いてるな」と感じる表現にも気づけるようになります。
- ちょっとした口語(例:なんとなく/たしかに/そうかも)
- 感情や迷いを含んだ語尾(〜な気がする/〜って思った)
- 場面を想像させる描写(例:コンビニのレジで〜、電車の中で〜)
こうした“人間っぽい言葉のクセ”を意識的にストックしておくことで、自然に文章に取り入れられるようになります。
複数ツールの併用で“AI臭さ”を薄める
1つの生成AIツールだけを使って書かれた文章は、どうしても文体や語彙の傾向が偏りやすくなります。
たとえばChatGPTならChatGPTらしい、GeminiならGeminiらしい“クセ”があるため、1ツール依存のままだと「AIっぽさ」がにじみ出やすくなってしまうのです。
そこでおすすめなのが、複数のAIツールを併用して仕上げる方法です。
- ChatGPTで構成・原案を作成 → Geminiで言い換えや視点追加 → 最後に自分で調整
- Claudeで自然な会話調に変換 → Perplexityで事実確認 → Grammarlyで言い回しを整える
など、異なるモデルの文体が混ざることで、結果的に“機械的すぎない、揺らぎのある文体”に近づきやすくなります。
しかも、チェックツールにかけたときに特定のAI文体パターンに偏っていないため、検出スコアが下がる傾向も見られます。
このように「AIを使うなら1つに絞る」のではなく、あえて“混ぜる”という選択が、人間らしい文章づくりに繋がるのです。
まとめ|チェッカーの裏をかくのではなく、“読まれても自然な文章”を目指そう
生成AIチェッカーは確かに進化していますが、それ以上に大切なのは「バレないこと」ではなく、“誰に読まれても恥ずかしくない、自分の言葉としての文章”を仕上げることです。
本記事では、以下のようなポイントを紹介してきました。
- チェッカーの判定ロジックと引っかかりやすい文章の特徴
- AIっぽさを消すための具体的なリライトテクニック
- 実例を通じた「機械文 → 人間文」への変換法
- 複数ツールを活用して“AI臭”を分散させる工夫
これらの知識と工夫を活かせば、生成AIを使いながらも読み手に「あなたらしさ」が伝わる文章を作ることは十分に可能です。
だからこそ、「AI使ったらダメかな」と悩むよりも、使いこなして、自分の言葉として昇華する姿勢が何よりも大切です。
AIはあくまで道具であり、最終的に責任を持つのはあなた自身。
だからこそ、ツールに頼ることを恥じる必要はありません。
堂々と、でも丁寧に。
それが、読まれても自然で、信頼される文章への一歩になります。
