
| この記事でわかること |
|
|---|---|
| この記事の対象者 |
|
| 効率化できる業務 |
|
2025年1月、NEC本社で、代表取締役社長・森田隆之氏が「生成AIとセキュリティの関係」について語りました。AI技術の加速に伴い、情報漏洩や不正アクセスといったリスクも拡大する現代に、NECは「セキュリティを内包したAI」という独自の戦略を打ち出しています。
ユーザーに寄り添い、安心して使える“真のAIエージェント”とは一体何なのか。その答えと、AIが変える未来像を一緒に探っていきましょう!
NECが描く「AI×セキュリティ」戦略の全体像
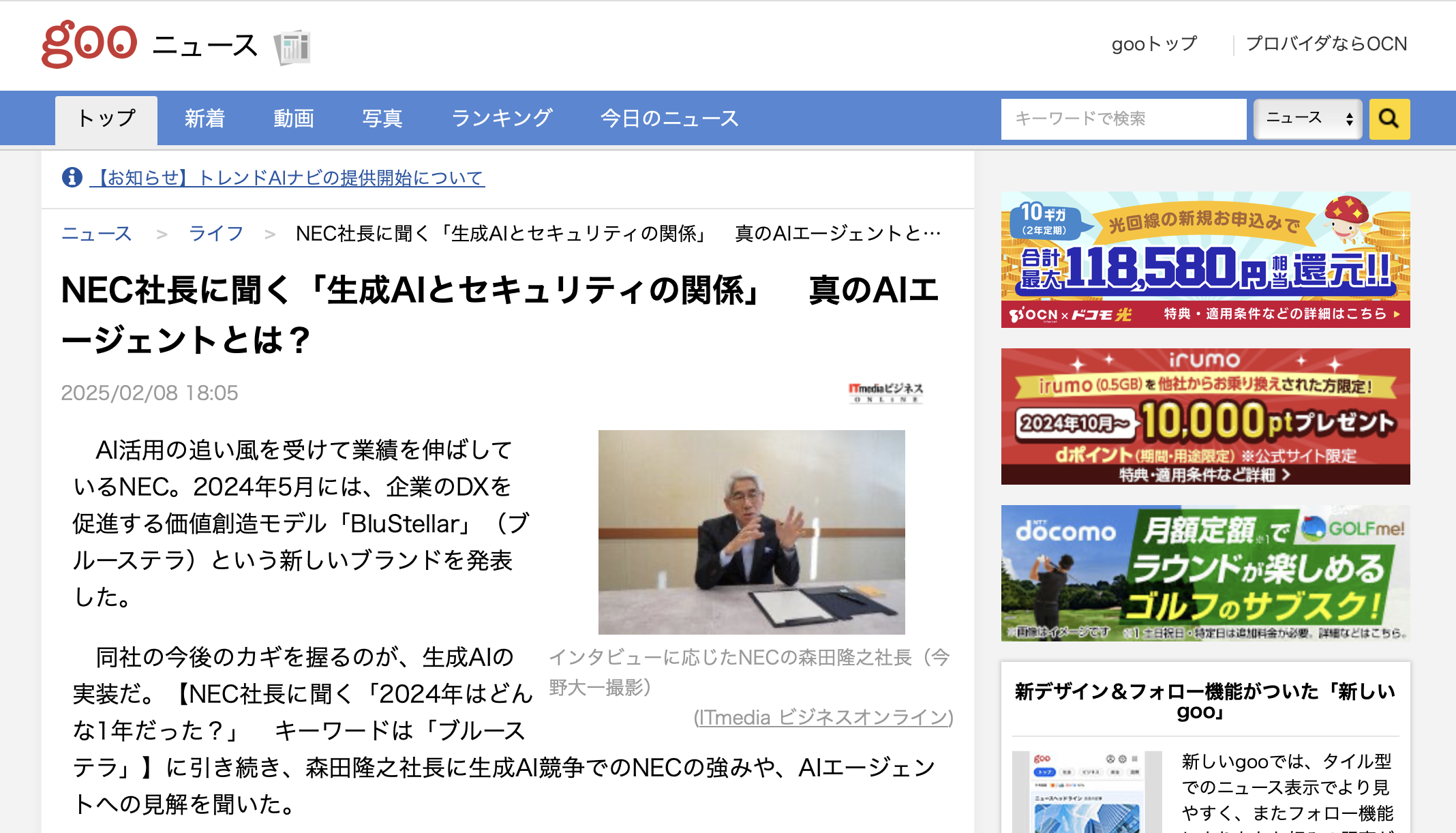
NECは、AIの力を安全に活用するために、セキュリティをAIに「内包」する独自戦略を掲げています。ただ便利なAIを作るだけではなく、安心して使えるAIを提供する。その姿勢が、今注目を集めているんです。
ここでは、NECが描くAIとセキュリティの融合戦略を深掘りしていきます。
生成AIの拡大とリスク意識の高まり
生成AIは、文章作成や画像生成など、業務効率を飛躍的に高めるツールとして広がっています。ただしその一方で、AIが引き起こす情報漏洩や不正アクセスなどの懸念も増大。2024年の国内調査では、企業の62%が「AI利用時のセキュリティ」に強い不安を持っているという結果も。
AIの成長に比例して、企業のリスク意識も急激に高まっています。現場では、セキュリティ対策の強化が最優先課題になりつつあり、特に、顧客情報の保護は最重要視されています。
セキュリティを“内蔵”する発想
NECは「セキュリティは後から付けるものではない」と考えます。AIの設計段階から安全性を組み込む、いわば“内蔵型”のアプローチが特徴です。
例えば、ユーザーが求める情報だけを処理し、それ以外は扱わない「選択的情報制御」や、不正な操作を即時検知する機能を導入。こうした設計により、運用時の負担を減らしつつ、高い信頼性を実現しているのがポイントです。このようにNECは、技術の根幹からセキュリティを捉え直し、新たなAI活用の道を切り拓いています。実際の製品にも、この思想が色濃く反映されています。
利用者目線の設計が信頼を生む
NECのAIは「技術推し」ではなく「利用者ファースト」。ユーザーの不安やニーズを理解した上で、安全性を確保しつつ、操作しやすい仕組みにこだわっています。
また、セキュリティ機能も“分かりやすさ”を重視。専門知識がなくても、直感的に使える工夫が施され、多くの企業から「使いやすい」と高評価を得ています。結果的に、導入のハードルもグッと下がるわけです。利用者に寄り添う姿勢が、NECの信頼の原動力となっているのは間違いありません。こうした工夫は導入後の定着率にもつながります。
真のAIエージェントとは?NEC社長の考える未来像

AIは、どこまで人に寄り添えるのか? NEC社長・森田隆之氏が提唱する「真のAIエージェント」は、単なるツールを超えた存在です。ユーザーの意図を理解し、先回りして支援する存在へ…。NECが描く“次世代のAI像”には、これからの企業運営や生活を大きく変える可能性が詰まっています。
「真のAIエージェント」とは
森田社長は、「AIがユーザーと並走し、常に最適な選択を導く存在」としてAIエージェントを定義しています。つまり、人間の代わりではなく、伴走者(パートナー)として動くAIを目指しているのです。
そのためには、情報処理だけでなく「文脈理解」や「共感能力」といった、人間的な感覚を持たせる技術が不可欠。AIが単に指示を実行するのではなく、行動の意図を“汲み取る”姿勢が求められています。
実現のカギはユーザー理解
「真のAIエージェント」を実現するうえで最も重要なのは、「ユーザー理解」の深さです。NECは、AIに人間の好みや行動傾向を学習させ、個々のニーズに合わせた対応を可能にしようとしています。加えて、AIが自ら学び、状況に応じて行動を最適化する「自己進化」の仕組みも導入予定。
こうした進化により、AIは単なるツールではなく、信頼できるパートナーへと成長するわけです。森田社長は、これが企業成長のカギになると語ります。
共感するAIが社会を変える
NECが目指すのは、「共感社会」を実現するAIエージェントです。人とAIが協調し、互いに理解し合うことで、働き方や暮らしの質も向上するという考え方。実際に、医療や教育分野でも共感型AIの実証実験が始まっており、その可能性は無限大です。
例えば、患者の気持ちを理解するAIや、学習スタイルに寄り添う教育AIなど。森田社長は、AIが“共に生きる存在”となることで、社会全体が優しくなる未来を描いています。
NECの技術的な強み
NECのAIは「セキュリティが標準装備」。他社と一線を画すのは、AI自体がセキュリティの役割を果たす点です。安全性と利便性を両立するNECの技術的優位性に迫ります。
AIが自ら守る“自己防衛型”設計
NECのAIは、セキュリティを「内蔵」した設計が最大の特徴です。例えば、通信データを常時監視し、不審なアクセスを自動でブロック。さらに、情報の取り扱いに応じて「アクセス権限」をAIが自律的に管理します。
こうした“自己防衛型”AIは、従来の「外部対策」依存型とは異なり、システム全体をシンプルかつ強固に守る仕組みを実現。AIそのものがセキュリティの司令塔を担っています。導入企業からは「安心感が違う」と高い評価を受けています。実際に、サイバー攻撃の検知率が飛躍的に向上したという事例も報告されています。
顔認証技術から得たノウハウ
NECは長年にわたり、顔認証技術で世界的な評価を得てきました。この技術で培った「リアルタイム処理」「高精度解析」のノウハウが、AIのセキュリティ強化に直結しています。
たとえば、不正なユーザー操作を即時検出し、AIが判断して遮断。しかも、判定の過程はすべて記録され、透明性を保った運用が可能です。
こうした高度な技術背景が、NECのAIを「安全性の高い実用的AI」に押し上げています。社内外の信頼構築にもつながる技術と言えるでしょう。これらの強みは、官公庁や金融機関でも高く評価されています。
運用のしやすさも重視
NECは、高度なセキュリティ機能を「いかに使いやすくするか」にも力を入れています。セキュリティ設定はシンプルなUIで直感的に操作可能。
さらに、自動アップデート機能により、常に最新の脅威に対応します。他社製品との互換性も意識した設計で、導入時の手間を最小限に抑えています。
高度だけど扱いやすい、これがNECの“技術×実用性”の融合力。運用担当者の負担を軽減し、現場の効率化にも貢献してくれるのが魅力です。結果として、導入後の定着率や満足度も非常に高くなっています。
生成AIのビジネス活用における注意点と対応策
便利なだけじゃ危ない!生成AI活用には落とし穴もあります。企業が安心して生成AIを使うには、事前のリスク対策が欠かせません。
ここでは、ビジネス導入時に押さえたい注意点と、NECによる安心サポートをご紹介します。
情報漏洩や誤情報の拡散
生成AIは、膨大なデータを基に文章や画像を生み出す仕組みです。その際、社内の機密情報をうっかり入力したり、不正確な内容が生成されたりするリスクがあります。特に、取引先の情報や顧客データが外部に漏れれば、大きな信頼損失につながります。
さらに、法的責任が発生する可能性もあり、企業にとって深刻な問題です。実際、情報漏洩による損害額は1件あたり平均4,600万円との調査もあります。加えて、生成AIによる誤情報の拡散が炎上の火種になることも。最近では、AIが生成した誤情報をSNSで拡散し、企業が謝罪に追い込まれた例もありました。
これらを踏まえると、リスク管理なしの運用は極めて危険です。導入前に具体的なリスクを洗い出し、備えを万全に整えることが重要です。
利用ルールとシステム面の強化
企業が生成AIを安全に使うには、「利用ルールの策定」と「技術的な制御」の両輪が必要です。まず、社内で入力禁止情報を明確にし、誤操作を防ぐルールを定めましょう。あわせて、ユーザー教育を行い、リスク意識を高めることも効果的です。
さらに、AIが扱うデータを制限し、アクセスログを自動記録することで、不正使用を抑止できます。NECでは、これらの対策をあらかじめ設計に組み込んだAIを提供しています。AIが自律的にリスクを検知し、リアルタイムで警告を出す機能も備えています。導入後のセキュリティチェックや運用サポートも充実しており、担当者の負担を軽減。こうした支援体制により、安心してビジネス活用が可能になります。
企業の成長を支える基盤として、NECのAIが注目を集めているのも納得です。
NECが目指す社会像とAIエージェントの役割
NECは「共感社会」の実現を掲げ、AIエージェントの活用を加速しています。技術の進化が人に寄り添い、社会全体に優しさをもたらす、その未来像に迫ります。
「共感社会」の実現とは?
NECが目指す「共感社会」とは、テクノロジーを通じて人と人が理解し合い、支え合う社会のことです。その中核を担うのが、AIエージェント。単に業務を自動化するだけでなく、人の気持ちや意図をくみ取り、最適な支援を行う存在として設計されています。
森田社長は「AIが人の良きパートナーとなる社会を作る」と語ります。AIが感情を理解し、共感を示すことで、人間関係や職場環境もより良くなる。そんな社会をNECは本気で実現しようとしています。
教育や医療分野では、すでに実証実験も進行中です。共感を軸にしたAIの活用は、国際的にも注目を集めています。NECは、この理念を企業活動の中心に据えています。
AIエージェントが変える働き方
AIエージェントは、単なるツールではありません。人間の仕事をサポートし、精神的な負担も軽減する“共に働く存在”です。
例えば、会議の記録や要点の整理、日程調整までをAIが自動化。これにより、人間は創造的な業務に集中できます。さらに、AIが利用者の感情や状況を把握し、タイミングよくサポートすることで、業務の効率も向上。
NECのAIは、ユーザーの声をもとに機能を進化させ、現場のニーズにフィットさせています。これにより、導入後の満足度も非常に高い傾向にあります。AIと共に働く未来は、すでに始まっているのです。NECは、働き方の変革を通じて、社会全体にプラスの影響を与えようとしています。
社会変化とAIの可能性
少子高齢化や人手不足が深刻化する中、AIエージェントの活用はますます重要になります。特に、医療や介護の現場では、AIによる支援が不可欠となりつつあります。
NECは、こうした社会課題にAIで応えるべく、持続可能なソリューションを展開。AIが「共感」と「支援」を軸に動くことで、人に優しい社会の実現が期待されています。
また、災害時の情報支援や高齢者の生活サポートなど、幅広い分野でAIエージェントの活躍が進んでいます。NECは、単なる技術革新にとどまらず、社会課題の解決にAIを活用。未来の社会像を描き、それを現実に変えようとしています。この挑戦が、新たな可能性を切り拓いています。
まとめ
NECが掲げる「AIとセキュリティの融合」は、単なる技術革新ではなく、社会全体を変える大きな一歩です。AIが人に寄り添い、共感しながら支援する——そんな未来は、すでに始まりつつあります。
安心してAIを活用するためには、企業の戦略や支援体制がカギ。NECの取り組みは、その好例と言えるでしょう。これからのAI活用、ぜひNECのアプローチを参考にしてみてください!








