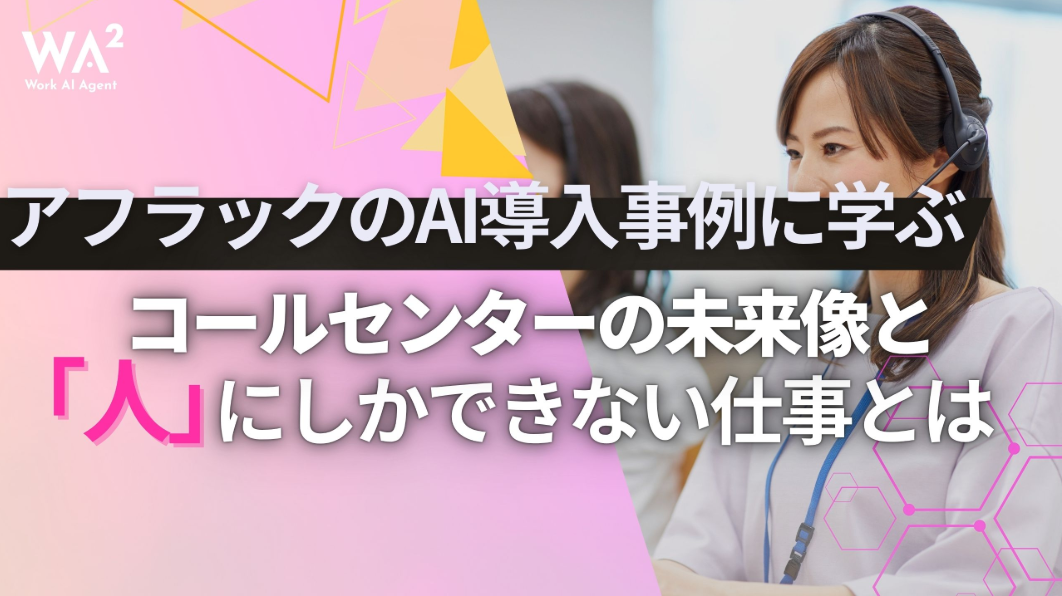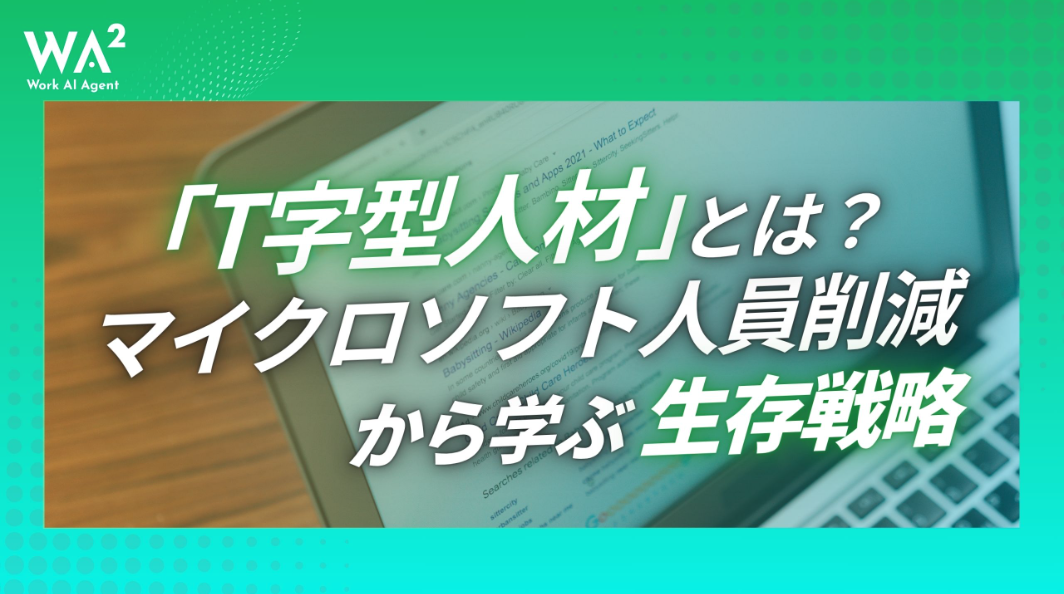こんにちは。AROUSAL Techの広報部です。
AI技術の進化は日々加速しており、企業の動向や規制の進展、教育分野への応用など、多くの注目すべきトピックが登場しています。
今週の主要なAIニュースとWA²でご紹介したAIニュースをまとめました。
それではやってきましょうー!
今週の主要なニュース
1.生成AI×マルチエージェントでチーム医療を再現、医師働き方改革へ一歩
Qsol株式会社と国立大学法人熊本大学は、2024年9月から進めてきた共同研究において、医療ガイドラインや電子カルテ情報を活用し、医師役・薬剤師役など複数のAIエージェントが協議するカンファレンスをシミュレートし、「チーム医療」を再現することに成功しました。この成果は、医師の長時間労働や地域偏在といった医療現場の課題解決に向けた第一歩であり、今後は類似症例参照の拡充や、自律的に情報検索を行う「Agentic RAG」技術の導入を通じて、多角的視点による医療支援機能の強化を目指します。
EUは2025年8月にAI規制法の一部を施行予定ですが、ASMLやSAP、エアバスなど欧州の大手企業44社が「準備が間に合わない」として2年間の延期を求めています。特に生成AIに関する規制が複雑で、企業の負担が大きい点が問題とされています。企業は明確なルールやガイドラインがないままでは、開発や競争力が損なわれると懸念。EUは年内に実践的なルール作りを進めていますが、企業側は施行前に詳細な説明を求めています。規制と技術革新のバランスが問われています。
3.京都芸術大学とシャープ、AI学習支援デバイス「Neighbuddy」の実用化に向けて前進
京都芸術大学とシャープは、AI学習支援デバイス「Neighbuddy(ネイバディ)」の実用化を目指しています。首にかけるだけで会話できる本機は、エッジAI技術を活用し、学生の学びをリアルタイムで支援。すでに授業で試験導入されており、音声対話の機能強化や2025年度の実用化に期待が高まります。
4.米上院、AI規制の州権制限案を否決:連邦主導から州独自の対応へ
2025年7月1日、米上院は、州によるAI規制を10年間禁止する法案を99対1で否決しました。 この法案は、連邦政府がAI規制を一元化し、州の独自規制を制限することを目的としていました。 しかし、子どもの安全やアーティストの権利保護を重視する声が高まり、超党派の反対により撤回されました。 これにより、カリフォルニア州やニューヨーク州などが進める独自のAI規制が継続可能となり、各州の対応が注目されています。
WA²でご紹介したニュース
「誰でも業務アプリを作れる時代へ」Create.xyzが描くノーコードの未来
エンジニアでなくても、直感的に業務アプリを作れる――そんな未来を実現するノーコード開発プラットフォーム「Create.xyz」。本インタビューでは、日本市場での成長やAIによるセルフサービス型への進化、直感的なUI設計の工夫、豊富な外部連携機能、そして“誰もが作り手になれる世界”というビジョンについて、Kinako氏が語ります。ノーコードの今とこれからを知る一歩として、ぜひご一読ください。
AI導入で成果を出す「はじめの一歩」。「戦略×診断×育成」でAI活用が定着する方法とは?
AI導入に挑戦するも、社内定着に課題を抱える企業は少なくありません。本記事では、経営視点の戦略設計から現場育成までを一気通貫で支援する「戦略×診断×育成」の三位一体アプローチを解説。CAIO(Chief AI Officer)の設置、AIアセスメントによる現状把握、OJTによる現場支援など、PoC止まりを防ぎ、AI活用を定着・成果に結びつける具体策を紹介しています。導入フェーズから事業価値創出へのヒントが満載です。
生成AIチェッカーにバレずに文章を書くには?AI使用だと思われないための5つの対策
生成AIを活用して文章を作成したものの、「AIで書いたとバレないか不安…」と感じた経験はありませんか?本記事では、AIチェッカーの仕組みと検出されやすい文の特徴を解説し、自然な文章に仕上げる5つの具体的な対策を紹介します。一文のリズム調整や体験談の挿入など、読み手に“人間らしさ”が伝わるリライト術を実例付きで解説。安心して文章を提出・公開したい方に必見の内容です。
なぜ日本は取り残されるのか?生成AI活用、世界最下位の衝撃と逆転への道すじ
PwC調査で明らかになった日本の生成AI導入率“世界最下位”という衝撃。本記事では、経営層の無関心・失敗を恐れる文化・現場のスキル不足という3つの壁を指摘し、その乗り越え方を具体的に提案します。経営者・現場・社会が取るべき行動とは?「学び直し」と「小さな成功体験」がカギを握る、日本再起への道すじを探ります。悲観を希望に変える第一歩を、ここから始めましょう。
アフラックのAI導入事例に学ぶ、コールセンターの未来像と「人」にしかできない仕事とは
2025年度中にも、コールセンターでの問い合わせ対応業務の5割をAIに置き換える──。アフラック生命保険が打ち出したこの方針は、多くの企業、特に顧客接点を持つ部門に大きなインパクトを与えました。米OpenAIとの提携により、生成AIを本格導入し、顧客対応のあり方を根本から変えようとしています。
025年6月、マイクロソフトがクラウド部門「Azure」を中心に、エンジニアから営業、マーケティングに至るまで、数百人規模の人員削減を計画していると報じられました。これは、生成AI「Copilot」への投資を加速させるための戦略的なリソース再配分と見られています。
「巨大テック企業のリストラは他人事」と感じるかもしれません。しかし、この動きはAI時代における働き方の未来を象徴しており、すべてのビジネスパーソン、特にエンジニアと営業職にとって重要な示唆を含んでいます。
まとめ
今週のAI業界では、医療・教育・法制度・規制といった多様な分野で注目すべき動きがありました。
中でも話題となったのが、熊本大学とQsolによる生成AI×マルチエージェントを用いた「チーム医療」の再現。複数のAIが医師や薬剤師として協議することで、医療ガイドラインに基づいた判断支援が可能となり、医師の長時間労働や地域医療の課題解決に向けて一歩を踏み出しました。
一方、規制面ではEUが2025年施行予定のAI規制法をめぐり、ASMLやSAPなど欧州企業が「準備不足」を理由に施行延期を要望。米国でもAI規制を巡る州と連邦の対立が表面化し、各国で制度設計の難しさが浮き彫りとなっています。
また、ノーコード開発の未来を描くCreate.xyzのインタビューや、AI導入を現場に根づかせる「戦略×診断×育成」の実践的アプローチ、さらにはAIチェッカーに“バレない”自然な文章を書くためのリライト術など、実務に役立つ読み応えある記事も公開中です。
生成AIの普及が進む今、技術そのものだけでなく「どう使いこなすか」が問われる時代になっています。来週も、社会に浸透するAIの動きと、その裏側にある課題と挑戦を追いかけていきます。
それではまた来週!