
皆さん、こんにちは。
AROUSAL Tech.広報部です。
本日はAIを使用する時によく起こる「あの現象」についてしっかり知っていただける記事をご用意しましたので、ぜひ最後までご覧ください!
ChatGPTやGeminiなどの生成AIが急速にビジネス現場に広まり、日々の業務効率化に役立てている方も多いはず。
しかし「それっぽく答えているけど、実は間違っていた…」そんな経験はありませんか?
この“もっともらしいウソ”こそが、AI特有の現象「ハルシネーション」です。
見抜きにくく、気づかず使ってしまうと社内外に影響を及ぼす恐れもあります。
本記事では、ハルシネーションの仕組みや起きる理由、実際に起こったトラブル例、そして業務でAIを使う際に注意すべきポイントと対策をわかりやすく解説します。
ハルシネーションとは?AIが「それっぽくウソをつく」仕組み

生成AIを使っていて「なんだか自信ありげだけど、内容が事実と違う…」と感じたことはありませんか?
それがまさに「ハルシネーション」と呼ばれる現象です。
ここでは、ハルシネーションの基本的な意味と、その背景にあるAIの仕組みをわかりやすく解説します。
ChatGPTやGeminiが“でまかせ”を言う理由
ハルシネーションとは、AIが事実に基づかない情報を、もっともらしく生成してしまう現象を指します。
たとえば「存在しない法律」「架空の統計データ」「実在しない論文」などを、それっぽく提示することがあります。
この原因は、生成AIの学習方法にあります。ChatGPTなどのAIは、インターネット上の大量のテキストをもとに、文脈にふさわしい単語の“次の言葉”を確率的に予測しています。
つまり、事実を正確に参照しているわけではなく、「それっぽい答え」を“もっともらしく作っている”だけなのです。
そのため、たとえ質問に対して自信満々な口調で答えていたとしても、それが正しいとは限らないのです。
人間には見抜きにくいハルシネーションの特徴とは?
ハルシネーションが厄介なのは、人間にとっても自然で説得力のある文章として出力される点にあります。
特に注意が必要なのが、以下のようなパターンです。
- 「それっぽい用語や数字」が登場し、もっともらしく見える
- 知識が曖昧な分野では、指摘できず鵜呑みにしがち
- 質問があいまいだった場合、“無理やり答えを作る”傾向がある
こうした特性から、AIの出力をそのまま業務で使うと、誤解やミスの原因になるリスクがあります。
特に、社外への資料やレポート、上司への報告書などでは注意が必要です。
実際にあった!ハルシネーションによるトラブル事例
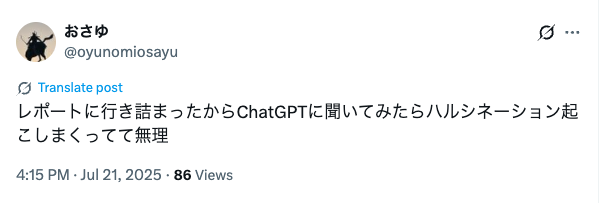
ハルシネーションは、単なる“ちょっとしたミス”で済まないケースも少なくありません。
ビジネスの現場では、誤情報が信用や成果に直結するリスクもあるため、事例から具体的に学ぶことが大切です。
ChatGPTを使って裁判に挑んだ弁護士の例

2023年、米国の弁護士スティーブン・シュワルツ氏が、航空会社の乗客が起こした人身傷害訴訟の準備のため、ChatGPTに法的調査を依頼。
AIが提示した6件の過去の裁判例を引用して準備書面を裁判所に提出しましたが、後にその全てがChatGPTによって捏造された架空の判例であることが発覚しました。
この行為により、シュワルツ弁護士と彼の法律事務所は裁判所から5,000ドルの罰金を科されました。
この事件は、専門家でさえAIの生成したもっともらしい嘘に騙される危険性を示しました。
ChatGPTによって犯罪者に仕立て上げられてしまった司会者の例

ラジオ番組の司会者であるマーク・ウォルターズ氏が、ある訴訟に関する情報をChatGPTに尋ねたところ、「ウォルターズ氏が財団から資金を横領した」という虚偽の情報を、架空の告訴状まで創作して回答されました。
これを受け、ウォルターズ氏は名誉を毀損されたとして、開発元のOpenAIを相手取り訴訟を起こしました。
このように、ChatGPTは「わからない」とは言わず、質問に対して無理やり回答を出す傾向があります。
そのため、引用や数値は必ず信頼できる出典で裏取りすることが必須です。
業務で使うときに注意すべきポイント
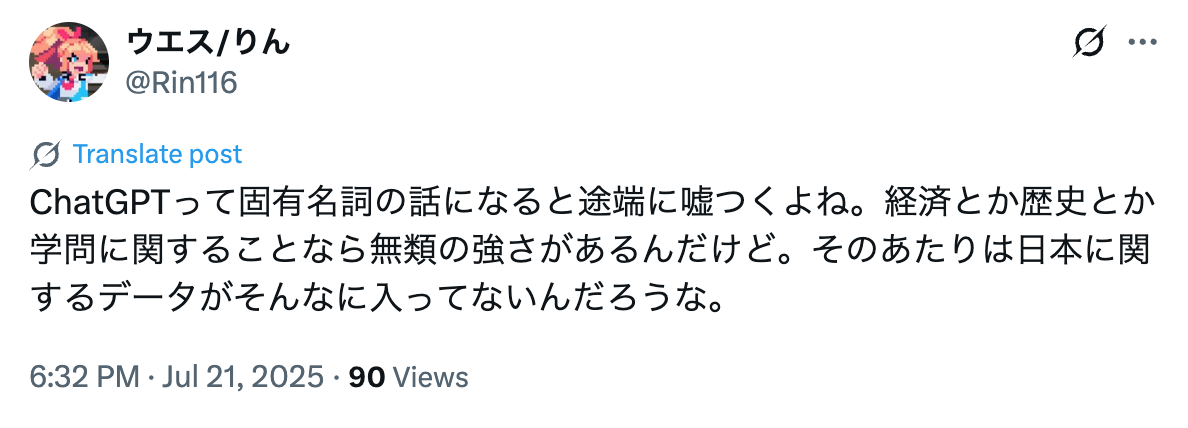
生成AIは非常に便利ですが、そのまま業務に使うにはリスクも伴います。
特にハルシネーションの影響を最小限に抑えるために、以下のような観点での注意が必要です。
AIの出力は“下書き”として扱うのが基本
AIが生成した文章は、あくまでアイデアやたたき台と考えるべきです。
そのままコピペで社内外に提出すると、誤情報や不正確な内容が含まれていても気づけない可能性があります。
特に業務では、人間の目による最終チェックは必須。
「内容の妥当性を誰が確認したか」が、社内的にも問われる時代です。
情報ソースが明示されないものは要確認
ChatGPTなどの生成AIは、命令しない限り学習元の出典を明示しません。
そのため、たとえば「参考文献」や「出典元」が書かれていても、それが実在するかどうかは自分で確認する必要があります。
とくに注意したいのは以下のような情報です。
- データや統計数字(架空である可能性あり)
- 論文や法律、制度など(出典元の確認必須)
- 商品・サービス名(実在しない、または誤認の恐れあり)
特に注意が必要な業務領域(人事・法務・医療・教育など)
以下のような領域では、ハルシネーションによる誤情報が信頼・倫理・法的責任に直結します。
- 法務・契約書作成:条文の誤りや存在しない規定の挿入
- 人事・労務領域:労基法や社内規定を“それっぽく”作られる
- 教育分野:学生に誤った知識を伝えてしまうリスク
- 医療・ヘルスケア:重大な健康被害や誤認の恐れ
これらの分野では、AIを使う=必ず人間のチェックを挟むという運用ルールを事前に整えることが重要です。
ハルシネーションを防ぐ/減らすための使い方のコツ
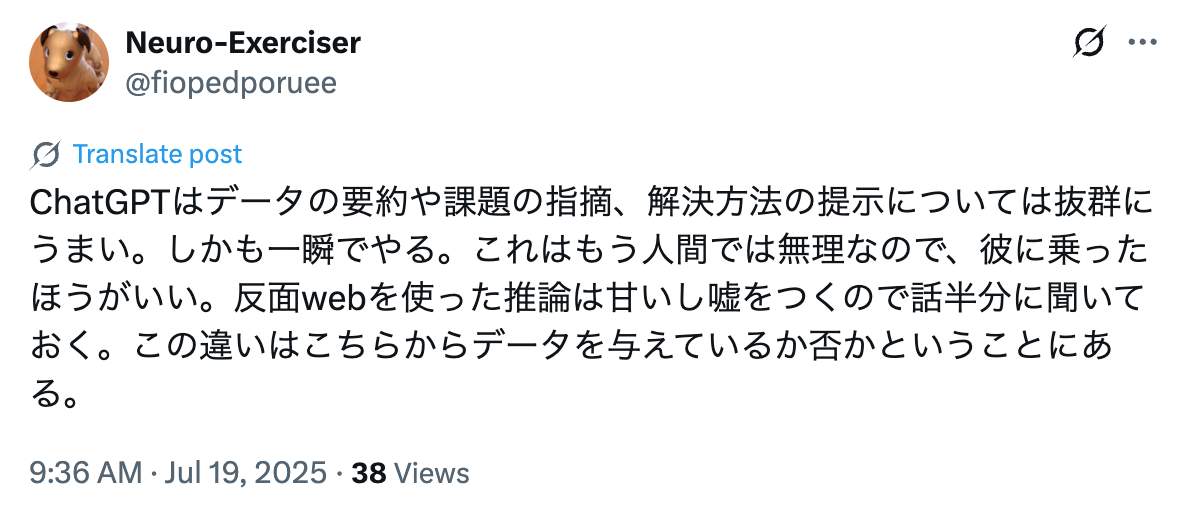
AIを安全かつ有効に活用するためには、ただ使うのではなく「どう使うか」が重要です。
ここでは、ハルシネーションの発生を抑えるための具体的なテクニックをご紹介します
「事実を聞く」より「意見や要約」に使う
ChatGPTは“事実”を正確に再現することは苦手ですが、文章の要約や言い換え、アイデア出しは得意です。
そのため、以下のような使い方が適しています。
- ニュースや資料の要約・かみ砕き
- プレゼン資料の骨子づくり
- アイデア出しやブレストの壁打ち
逆に、「〇〇の法改正はいつ?」「〇〇の論文はある?」といった事実確認を丸投げするのは避けるべきです。
1つの質問を複数のツールでクロスチェック
ChatGPTだけで完結させず、複数のAIや検索エンジンを併用することでハルシネーションの誤認リスクを大幅に下げられます。
おすすめの併用方法は、以下のとおりです。
- ChatGPTに投げかけた質問をGemini(Google系) にも聞いてみる
- AIが挙げた用語や事例を、Google検索でファクトチェック
複数のツールで同じ内容が出てくる場合は、信頼性が上がると判断できます。
出力を信頼できる人間がレビューする体制をつくる
最終的な防波堤になるのは、やはり人間の目。
特にチームでAIを使う場合は、「生成した内容を誰が確認するか」を明確にルール化しておくことが重要です。
- AI出力に対して、専門知識を持った担当者が目を通す
- 重要な資料は、必ず “人間レビューを経て提出” をルールに
- 社内で「誤情報によるトラブル」事例を共有し、注意意識を高める
これにより、「知らずに誤情報を使ってしまう」ことを大きく減らせます。
まとめ|ChatGPTは万能ではない。でも、使い方次第で強い味方に
生成AIは、私たちの業務に革新をもたらす一方で、「ハルシネーション」という見えにくい落とし穴を内包しています。
もっともらしい文章で、事実とは異なる回答をする──これはツールの仕様であり、使う側が理解しておくべき前提条件です。
ただし、だからといって「使えない」と切り捨ててしまうのは早計です。
AIは“情報の決定者”ではなく、“提案者”として使うことが前提。
要点の整理やたたき台の作成、発想の壁打ち相手として活用すれば、十分に強力なパートナーとなります。
「怖いから使わない」ではなく、「正しく使えば頼れる」——AIとのつきあい方は、そこにあります。








