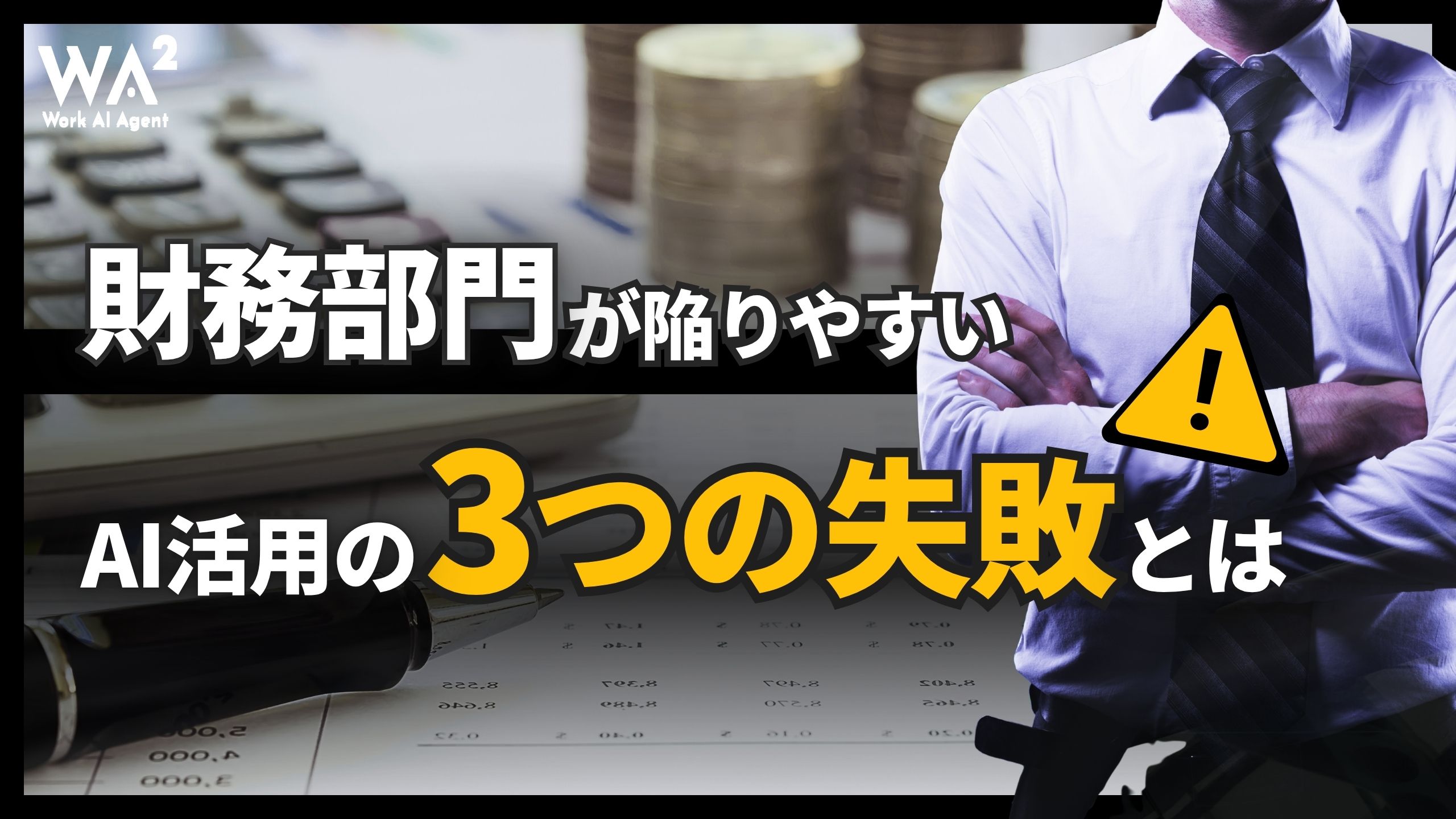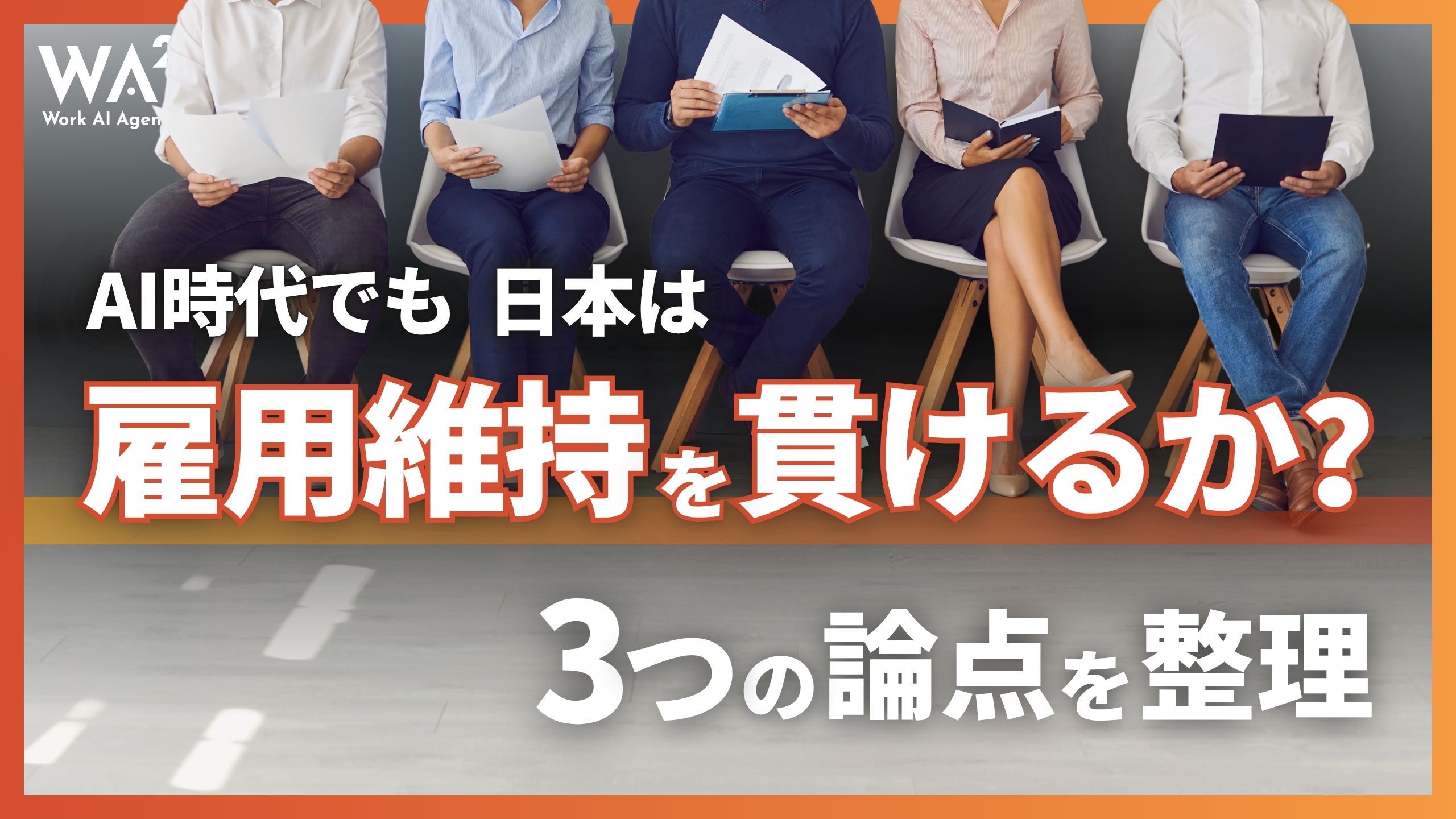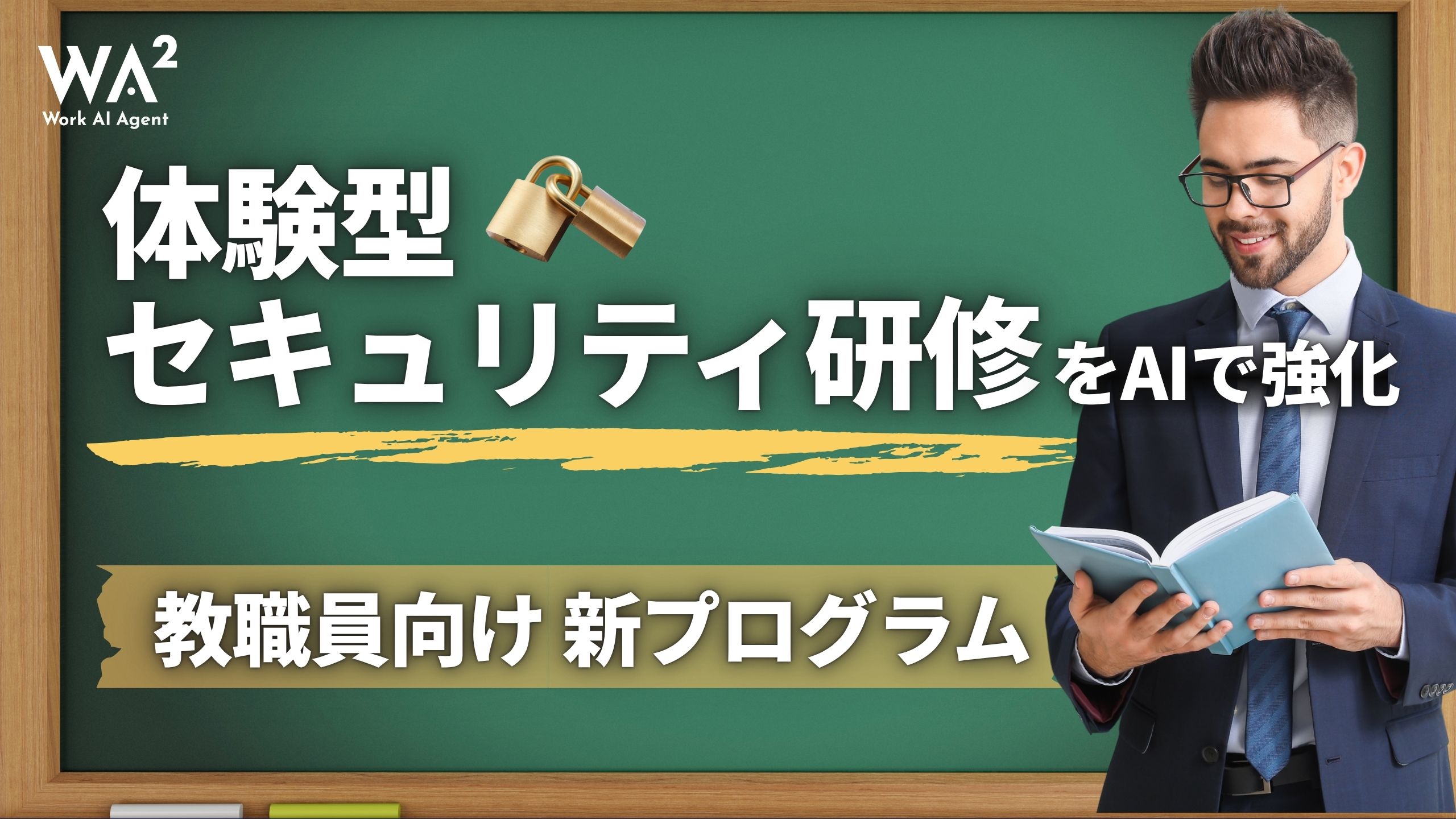こんにちは。AROUSAL Techの広報部です。
AI技術の進化は日々加速しており、企業の動向や規制の進展、教育分野への応用など、多くの注目すべきトピックが登場しています。
今週の主要なAIニュースとWA²でご紹介したAIニュースをまとめました。
それではやってきましょうー!
今週の主要なニュース
1.Pinterest、AI生成画像の“露出抑制”機能を導入 ユーザーが選べる表示頻度調整へ
Pinterestは近年増加するAI生成コンテンツへの批判を受け、ユーザーがAIによる画像の“表示を減らす(see fewer)”設定を使える新機能を導入しました。まずは「美容」「アート」といったAI画像が多いカテゴリで試験運用され、ピン右下の三点メニューから選択可能です。さらに、AIで生成または編集された画像には「AI修正済み(AI modified)」というラベルが自動で表示され、誤ラベル時には異議申し立てもできる仕組みです。Pinterestはメタデータ解析と独自AI分類器を組み合わせて透明性を高め、ユーザー体験の質を守ろうとしています。
2.ANAが生成AIで業務効率を大幅改善:オペレーション部門での横断展開
ANAは、自社クラウド環境で生成AI「neoAI Chat」を導入し、空港・整備・客室・運航といった複数部門に展開しています。このAIは社内規程や議事録などの文書を横断的に検索できるため、これまで時間がかかっていた情報収集の工程を約9割短縮しています。また、報告書や教育資料などの定型文書もAIによって自動作成が進み、作成時間を約75%削減しています。従来は担当者の経験に依存していた知識共有をAIが補完することで、現場の判断スピードが向上し、人材をより付加価値の高い業務へ再配置しやすくなる効果が期待されています。
3.JR東海、新幹線カメラ映像をAI分析へ ― 利用目的推計の実証実験
JR東海は、東海道新幹線の車内防犯カメラ映像をAIで分析し、乗客の利用目的を推計できるか検証する実証実験を2025年11月に実施すると発表しました。対象となるのはN700Sの1号車・6号車・8号車で、各車両には6台のカメラが設置されています。映像から年代・性別・服装・持ち物などの特徴を抽出し、「ビジネス」「観光」「インバウンド」などの乗車目的を統計的に分類する仕組みを検証します。データは本検証以外には使用せず、終了後には削除される方針で、個人を特定しない運用を徹底すると説明されています。今回の取り組みは、防犯用途にとどまらず、運行サービスや利用動向の把握にAIを活用する新たな試みとして注目されています。
4.UAE発G42、ホーチミン市でAIデータセンター構想を始動
アラブ首長国連邦の先端技術企業G42は、ベトナムのホーチミン市で大規模AIデータセンターの建設を地元IT大手FPTなどと共同で提案しました。この構想は、東南アジアで高まる生成AIやクラウド需要に対応する戦略的プロジェクトとして位置づけられています。さらに、UAE政府系ファンドやマイクロソフト、ベトナムの投資ファンドが参加を検討しており、国際連携によるインフラ整備が進む見通しです。実現すれば、ベトナムのデジタル経済を加速させるだけでなく、日本企業を含む海外勢のビジネス展開にも波及効果が期待されます。
WA²でご紹介したニュース
財務部門が陥りやすいAI活用の3つの失敗とは
財務部門でのAI活用は期待が高まる一方で、「導入したのに成果が出ない」「現場に浸透しない」といった失敗が多発しています。本記事では、ありがちな3つの失敗――目的なき導入、放置されたデータ品質、現場のAIアレルギー――を具体事例とともに解説。さらに、成功企業の取り組みや定着のポイントも紹介し、財務DXを実現するための実践的ヒントを提供します。
AI時代の日本は雇用維持を貫けるのか。本文では、①仕事の「代替」ではなくAIとの「協働」が進む現実、②メンバーシップ型雇用の防波堤/足かせという二面性、③失業なき労働移動とリスキリングの壁を、データと現場の声で検証。事務の自動化や分析高度化の効果を踏まえ、配置転換・評価制度・学びの仕組みまで実務的処方箋を提示。経営者・人事・働く個人の意思決定を後押しします。
年1回で形骸化しがちな情報セキュリティ研修を、対話型AIで“体験学習”へ刷新。教職員が疑似インシデントに応答しながら判断力を鍛え、テストで終わらない「咄嗟に動ける」力を習得します。設計工数・運営コストを抑えつつ理解度を可視化。スモールスタートで効果検証→全校展開、生成AI悪用のフィッシング等にも対応できるカリキュラムとPDCAで、学校組織に自走するセキュリティ文化を根付かせます。
画像生成AI対決、Seedream4.0はNano Bananaを超えたのか
画像生成AIの実力を比較し、Seedream4.0はNano Bananaを超えたのかを多角的に検証します。写実性・指示忠実度・生成速度・安全性・コストの5指標でテストし、強みと弱点を明確化。広告・広報での使い分け、企業利用でのガバナンス要件、プロンプト最適化の勘所も解説。単なる勝敗でなく「用途起点」で最適解を導く実務者向けレビューです。
コロプラが生成AI「AI社員」の活用率90%超を実現。3人に1人が業務量半減を実感した背景を、①経営トップ直轄の推進体制、②全社巻き込みのAI活用コンテスト、③独自LLMでのセキュリティと利便性両立――の3施策で解剖。議事録・翻訳・要約など横断業務の効率化事例を示し、DX推進・人材育成・業務プロセス改善の実践ポイントを提示します。
ChatGPTやGeminiといった生成AIの登場が、私たちの情報収集、そして「買い物」の形そのものを根底から覆そうとしているのです。企業のマーケティング担当者として、こんな不安を感じていませんか?
「SEO対策を頑張ってきたけど、AIが答えを出すなら、自社サイトへのアクセスは減るのでは?」「消費者はこれから、どこで、どうやって商品の情報を見つけるようになるんだろう?」この記事は、そんな漠然とした不安を解消し、AI時代の新しい消費行動にいち早く対応するための具体的な戦略を解き明かします。
まとめ
今週のAI業界では、ユーザー体験・インフラ整備・業務DXの3領域で実装が進みました。PinterestはAI画像の表示制御機能を導入し、透明性と倫理面を強化。国内ではANAが生成AIを全社展開し、文書作成や情報検索を大幅に効率化しました。JR東海は新幹線カメラ映像のAI分析による利用目的推計の実証を開始し、サービス活用への応用が期待されています。
グローバルでは、UAEのG42がベトナムでAIデータセンター構想を始動。マイクロソフトなども連携を検討しており、東南アジア発のAIインフラ拡大が加速しつつあります。
また、WA²では企業や教育現場でのAI活用事例を特集しました。財務部門の導入失敗要因や、日本企業の雇用維持に向けた協働型AIの可能性、体験型セキュリティ研修、新モデル比較、そしてコロプラの活用率90%事例など、実務視点での示唆が多く得られる内容となっています。
AIの進化と社会実装が同時並行で進む今、企業・行政・教育の各現場が「どう活かすか」「どう備えるか」というフェーズに入りつつあります。
来週も、国内外の動きと活用知見をわかりやすくお届けします!